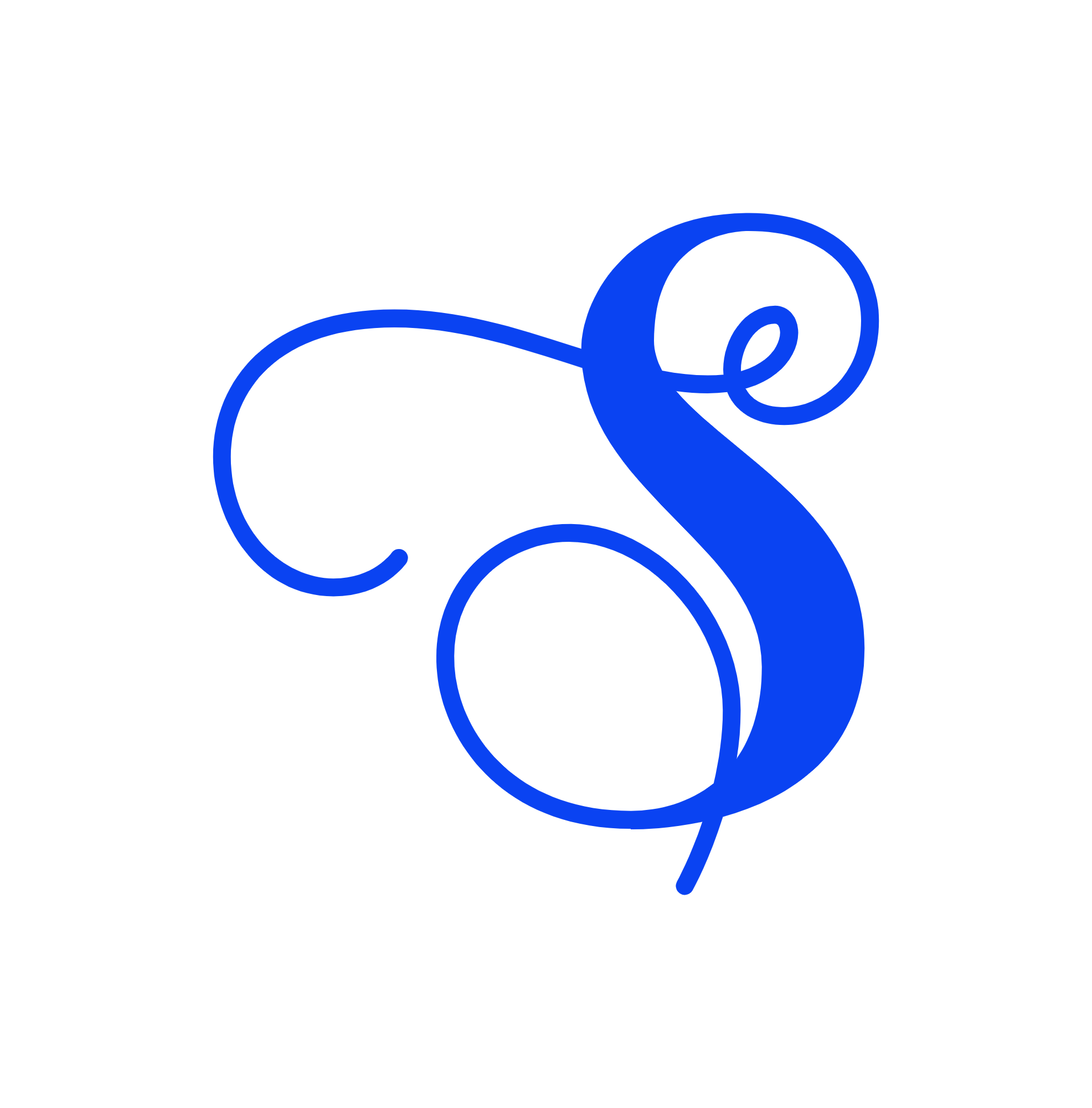海外の消防法と日本の消防法の比較
こんにちは!!
メジャーリーグの大谷選手の活躍が凄すぎますね(*´ω`)彼の現役時の活躍を見ることが出来るのは幸せです。
WSが始まるのが楽しみです♪
そんな海外で活躍する日本人を見て私も海外で消防法や消防設備はどうなっているんだろうという疑問が浮かびました。
今回は本やウェブサイトで調べたことをまとめます。
私個人の主観も含まれているので参考程度にしてください(笑)( *´艸`)
海外の消防法と日本の消防法には大きくいくつかの違いがあります。
まず日本の消防法は「予防重視型」であり、火災を未然に防ぐための設置基準や点検義務が非常に細かく規定されています。
これは日本の消防設備業に携わる方なら実感があると思います。
例えば感知器やスプリンクラーの設置義務、避難経路の幅や非常灯の明るさまで細かく規定されています。
これに対して海外、特に欧米諸国では「自己責任型」「性能規定型」が多く、
建築基準法や消防規則を守りつつも具体的な設備の種類や設置方法は建築士や設計者に委ねられるケースが多いそうです。
そのため最新の防火技術や設計思想を柔軟に取り入れやすい一方、国や地域によって基準のばらつきがあります。
また、アメリカではNFPA(全米防火協会)の規格が国際的にも広く用いられており火災リスクを科学データに基づいて評価するアプローチが主流です。
ヨーロッパもEN規格を採用し、建材の耐火性能や避難安全性を重視しています。日本は戦後の火災多発を背景に全国一律の強い規制を整備した経緯があり
現実の実務としては「世界の中でも特に厳しい基準」といわれます。
つまり、日本では「細則で縛る方式」、海外は「性能を満たせば方式は問わない方式」という違いが大きな特徴です。
これらの違いには各国の建物の構造や地質的な事情など多くが関わってくると思います(`・ω・´)
日本の場合
住宅や中小規模建築物に木造が多く、密集した市街地も多い為「延焼を防ぐ」「避難を確実にする」という視点で規制が厳しくなっています。
その為、上記でも述べたとおりに防火区画(耐火壁・防火戸)、感知器の設置義務、避難経路の幅や階段の構造などが細かく決められています。
また地震が多い国なので耐震と防火を両立させる必要があり、耐火建材や耐震設計の組み合わせが法律で求められています。
海外の場合
欧米は鉄骨造・RC造など不燃性の建物が主流で都市計画上も区画が広い為「延焼リスク」が日本ほど高くはありません。
その分、建物性能や火災時の避難安全性に重点が置かれ、必ずしもすべてにスプリンクラーや感知器を義務付けるわけではなくリスクに応じた設計が許されます。
アメリカや欧州の高層ビルでは耐火構造を前提に「煙制御」や「避難計画」のシナリオが重要視されます。
以上の事から
日本は「木造密集地+地震国ゆえに細則で守る」、
海外は不燃建築+区画の広さを前提に性能基準で柔軟に対応」という構造的背景の違いが消防法の違いに繋がっていると言えます(´・ω・`)
正直どちらもいいところがあると思いますが、命を守る為の設備なので厳しく細かい方が私としては安心できます(笑)
株式会社 新星設備では消防用設備の点検、改修工事、照明器具や換気扇工事、ポンプの交換工事等を行っています。
誠心誠意対応致しますのでお問合せより連絡をお待ちしております(=゚ω゚)ノ
前の記事へ
« 消火器の廃棄方法次の記事へ
2025年 秋 岐阜旅行 »